「鬱は大人の嗜みですよ。」
~リリー・フランキー~
すごく素敵な言葉だと思います。
僕も鬱を経験していて、寛解(かんかい:症状が治まり穏やかであること)しているものの時折うつ症状の波がやってくることがあります。
その時はリリーさんの言葉を思い出すと「あ、いまは嗜んでいるんだ」と距離を取ることができます。
でも、鬱についてよく知らないままだと、押し寄せる波に生身で真正面から飛び込むことになります。これは非常に危険です。
自分が今いったいどんなものに巻き込まれているのか、巻き込まれている中でどんな選択を取ればいいのか。
ある程度その対象について知っておかないと危険にさらされたり、大切なものを失ってしまう原因になってしまいます。
そうしていればあの日、休職してクローゼットの奥から引っ張り出して来たPSPを日が昇り沈むまで訳も分からず泣きながらプレイしていた自分も少しは楽だったはずです。
そこで今回は、今まさに鬱を嗜んでいる人、これから嗜む予定のある人に向けて
「そもそも鬱ってなんだ」というところから「そうだったのか」と思うような部分まで解説していきたいと思います。
うつ病の定義
うつ病は「なんとなく気分が落ち込む」といった一時的な状態ではなく、医学的な診断基準があります。
【DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版)では以下のように基準が定められています】
アメリカ精神医学会がまとめた DSM-5(精神障害の診断と統計マニュアル第5版) では、以下のように定められています。
以下の症状のうち 5つ以上 が、2週間以上続く ことが条件とされています。また、そのうち1つは「抑うつ気分」または「興味・喜びの喪失」である必要があります。
- 一日の大半、気分が落ち込んでいる
- ほとんどの活動への興味や喜びがなくなる
- 食欲が減ったり、逆に食べ過ぎてしまう(体重変化)
- 眠れない、または眠りすぎる
- 落ち着きがなくソワソワする、または動きが鈍くなる
- 疲れやすく、気力が出ない
- 自分に価値がないと感じたり、過剰に罪悪感を抱く
- 集中力が落ちたり、決断ができない
- 死について考えたり、自殺を考える
これらの症状が生活に大きな支障をきたしている場合、うつ病の可能性が疑われます。
【ここで注意点!!】
上記はあくまで専門家が診断を行う際の参考基準です。
「5つ当てはまるから自分はうつ病だ」と自己診断することは危険です。
実際の診断には、医師が症状の経過や生活背景、他の病気の有無などを含めて判断します。
「当てはまるかも」と感じたときは、一人で抱え込まず、まずは心療内科やメンタルクリニックに相談してみてください。
相談先がわからない場合は、以下のような窓口もあります。
- いのちの電話(全国共通ダイヤル:0570-783-110)
- 厚生労働省・こころの健康相談統一ダイヤル:0570-064-556
うつ病のとき脳内で何が起こっている?
うつ病とは「脳の炎症」と言われています。
鬱はその症状やそこから生じる支障に注目されがちですが、実際脳内では何が起きているのでしょうか。
神経伝達物質のアンバランス
これらがバランスを崩すことで、「気分の落ち込み」「興味の喪失」が生じると考えられています。
セロトニンの生成を増やすためには「腸活」お勧めします。
脳の部位の働きの変化
- 前頭前野(考える・判断する部分)
→ 活動が低下し、集中力や決断力が落ちる。 - 扁桃体(不安や恐怖を感じる部分)
→ 過剰に活動し、ネガティブな感情が強まりやすい。 - 海馬(記憶を司る部分)
→ 小さくなる傾向が報告され、過去の失敗を繰り返し思い出すなど「反芻思考」と関係している。
この脳の働きを良好にするには瞑想がお勧めです。
ストレスホルモンの影響
- 長期間ストレスを受けると、コルチゾール(ストレスホルモン)が過剰に分泌される。
- これが脳細胞を疲弊させ、特に海馬にダメージを与えるとされる。
あなたの習慣が知らずしらずのうちにコルチゾールを増やしている原因があるかも
脳内ネットワークの乱れ
- 最新の脳科学では、脳のネットワーク(神経回路のつながり方)がうつ病で変化していることがわかってきています。
- 「デフォルトモードネットワーク(ぼんやりしているときに働く回路)」が過剰に働き、否定的な思考にとらわれやすくなるという説もあります。
うつ病は脳内物質の量だけでなく神経や脳の構造も変化させてしまう病なんですね。
この期に及んで「うつは甘え」という考えを持っている人はいますよね。
自分がうつの渦中にいるとそんな時代錯誤な言葉にも振り回されてしまいそうになることもあります。
しかし、うつ病を引き起こす脳のメカニズムを知ると、「気の持ちよう」「甘え」というにはあまりに物理的で身体的な病気であることがわかります。
うつ病の時期ごとの特徴
うつ病には3つの段階があります
- 急性期
- 回復期
- 再発予防気
急性期(発症〜数週間)
この時期はうつ病になり最も症状の重い時期と言われています。
気分が極端に落ち込む
というような症状が現れ、日常生活にも影響するため心身ともに負担が大きいです。
身近な人に見守りをしてもらう必要がある場合もあります。
回復期(数週間〜数カ月)
- 適切な休養により少しずつ気分が安定してくる
- ただしまだ疲れやすい
- 気分の波がある(良い日と悪い日が交互に来る)
急性期よりも症状はだいぶ落ち着いてきます。
しかし無理に人に会ったり、仕事を復帰することは避けた方がいいでしょう。
軽い運動や散歩から少しずつ刺激を与えていくことが大切です。
維持期(半年〜数年)
- 気分の波が緩やかになる
- 依然としてストレスに弱く再発リスクがまだ高い
- 日常生活はほぼ普通に遅れる
この時期の症状は日常生活を送る分には問題ないくらいの負担感です。
再発の芽を早めに察知できるように感情の波やコンディションをセルフチェックしましょう。
再発予防期(寛解後〜長期)
- 普段通りの生活ができる
- ただし「再発しやすい脳の傾向」は残っている
- ストレスや環境の変化で再び症状が出ることがある
いわゆる寛解に当たります。
厳しい現実ですが、ここまで来ても再発のリスクは免れません。
しかしそれは自分は大切にするべきひとりの人間なんだという裏付けなのかもしれません。
自分を大切にできていなかった。大切にする仕方がわからなかった。
今まで通りの生き方をしていけばうつはまたすぐ影を見せます。
鬱から学べることの1つは自分は大切にすべき人間だったということです。
ちゃんと自分は壊れる。丁寧に向き合っていかなきゃだったんだ。
それを学ばせるためにここまで壊れる必要があったのだと実感しています。
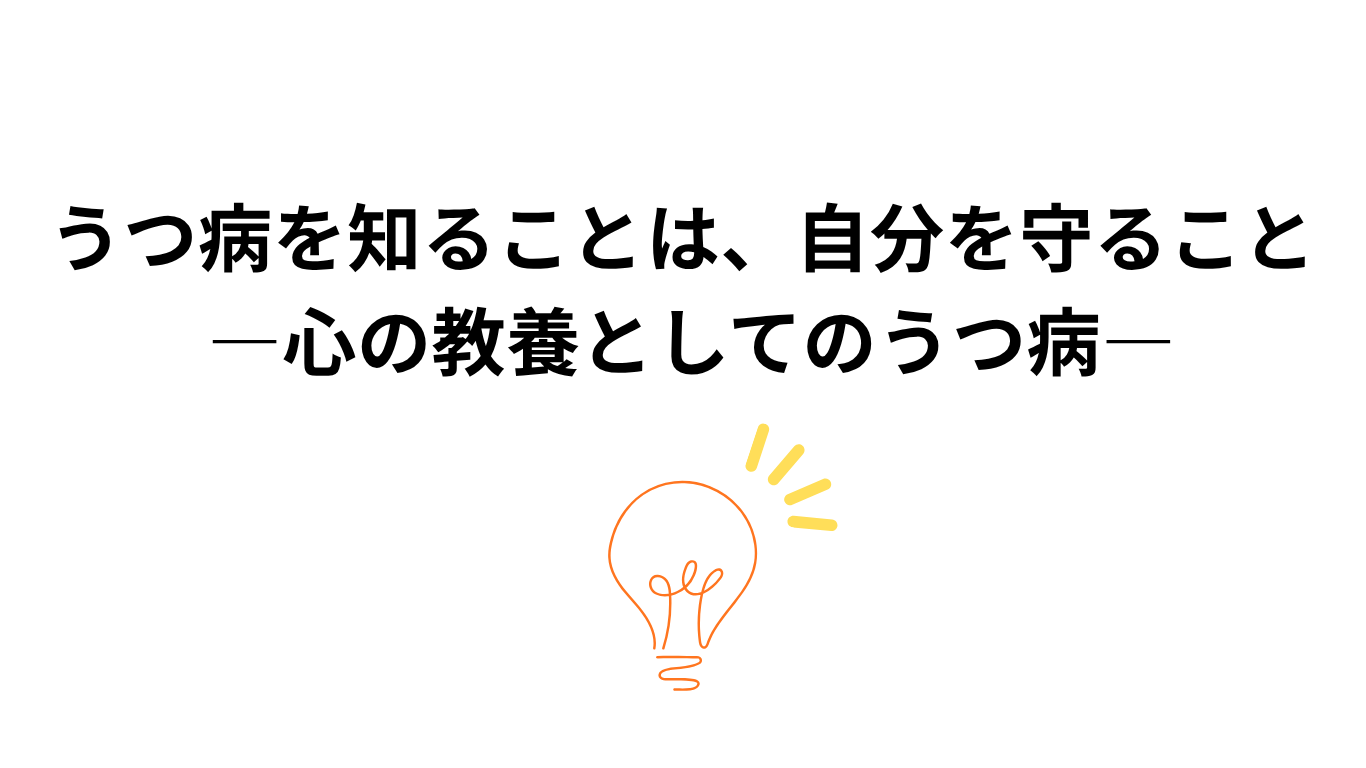
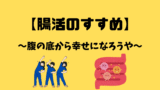

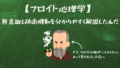
コメント